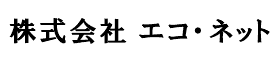四方を海に囲まれた魚食民族といわれた日本人。しかしその広い海を様々な規制の網で仕切られ、また捕獲技術の発展からその捕獲量も資源許容量ギリギリにまで達しており、今後は内海での‟つくり育てる栽培漁業”に大きな力点をおかざるを得ません。
そこで私たちは、次世代型養殖管理の構築を目指して、‟新鮮・安全・安心・本来のおいしさ”を合言葉に、成長促進剤や魚病対策抗菌剤などの投与を極力抑え、免疫賦活物質を応用した『微生物資材』の使用をお薦めしております。

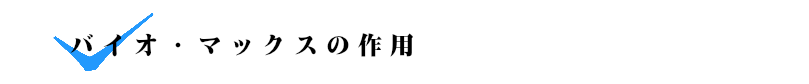
ー 魚介類の成長促進と斃死率の低下 ー
魚介類がバイオ・マックスを摂取することにより腸内環境が改善されます。これにより食物の消化・吸収が促進され、飼料効率が高まって大きく育ちます。
また腸内環境が改善されますと、有害細菌(悪玉菌)の活動が抑えられますので、悪性・悪臭物質や腐敗物質の生成の抑制につながります。
また乳酸菌には抗菌作用や免疫賦活作用が確認されており、病原菌に対する抵抗力や自然治癒力が向上します。更にこれらの作用は、抗生物質とちがい耐性をもたらしませんので、長期間の使用でも作用は維持されます。
近年『抗生物質を使用しない飼育法』として注目されています。
ー 水中環境の改善 ー
魚介類の糞尿や残餌は、時間の経過とともに分解されて、有害なアンモニアなどの窒素化合物になります。これがさらに変化して亜硝酸が生成されます。これら有害物質の水中濃度の上昇は飼育生物の死につながり、特に容量に限りがあるいけすや水槽では、海や河川に比べてその影響が顕著に表れるため、有害物質の濃度を速やかに下げることが求められます。
(魚は1ℓの水にアンモニアが0.005g含まれると死ぬことがあり、亜硝酸だと0.0005g程度で害を受けはじめ、さらにそれ以上になると死ぬことがあります)
バイオ・マックスにはこれらの有害物質を分解する作用がありますので、有害物質の濃度が低下して、いけすや水槽中の環境が改善されます。 (比較的弱いエビやアジでも弱りにくくなります)
バイオ・マックスの「より良い健康状態」「より良い環境」での飼育は、増体や肉質・匂いの改善と病気や斃死率の軽減をもたらし、「より良い生産」を可能にしてくれます
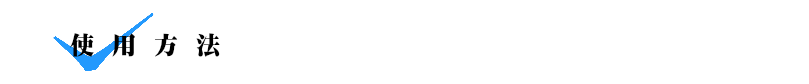
ー 餌に混合して与えます ー
餌の総量に対して5%相当量のバイオ・マックスを混合して投与します。ペレットなどの場合は、数分~数十分間バイオ・マックスに浸して(吸収させて)から投与します。
( バイオ・マックス量(ℓ)=餌量(㎏)×0.05 )
餌の量が多い場合は、淡水で希釈してから、餌全体にまんべんなく混合してください。
毎日の投与が理想です。また効果を維持するには継続が必要です。
※ 餌に混合すると、いけす・水槽に注入する必要はありません
ー いけす・水槽に注入します ー
初回(いけす・水槽の立ち上げ時)
いけす・水槽に水量の0.5%相当のバイオ・マックスを注入します。 ( バイオ・マックス量=水量×0.005 )
また濾過槽に水量の0.2%相当のバイオ・マックスを注入します。 ( バイオ・マックス量=水量×0.002 )
2回目以降(水替え時)
いけす・水槽および濾過槽に、初回投与量をもとに、替える水の量に相当する量のバイオ・マックスを注入します。
( バイオ・マックス量=替える水量×0.005(0.002) )
※ いけす・水槽に注入すると、餌に混合する必要はありません